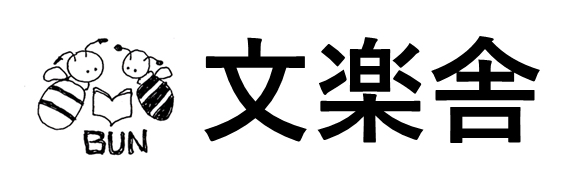-

あしたのために7
「禁止」を他人事と思わずに、「自分事」だととらえてみる。誰かから「禁止」されるものではなく、自ら「禁止」すべきものだと考える。ですから「禁止」は、禁止のすべてが不必要なのではなく、その場にいる子どもたち自身が納得のいくように作られるもの... -

あしたのために6
「禁止」を辞めました。禁止事項にはそれが成立するのに理由があるように、子どもがその禁止行為をしてしまう背景には、それなりの意味があるように思えたからでした。ただ「禁止」をしない日常では、ケンカが起きる、物が壊れる、せっかく作った料理が食... -

あしたのために5
「教える」ことを辞めました。これまで誰かの都合優先でなされてきた「指導」が、本来は面白いはずの「学び」から、学ぼうという姿勢を失わせ、子どもたちを逃避させてきたという側面があるような気がいたします。解法の手順を押し付けたり、手っ取り早く... -

あしたのために4
具体的な設計図の基に始めたのではなく、見切り発車のようにスタートした活動を、2015年には全面的に見直しました。子どもたちのためといいながら、それでも保護者の顔色をうかがう側面や、おとなの要求に応える部分があったのを辞めました。社会や世間の... -

あしたのために3
2013年、活動拠点を東京都に移転、自宅をリフォームし、家庭あるいは学校や塾とも異なる第3の居場所として開放しました。そして子どもたちがいつでも気軽に集える場所「文楽舎」を創設しました。そこではまず、「与えること」を辞めることから始めました... -

あしたのために2
2011年、東日本大震災での経験を機に、学習塾の看板を下ろすことにしました。ひと頃の塾生数に比べてその数が少なくなってきたとはいえ、在塾生の保護者の方々の反対は激しいものでした。一年という期間をかけて、何度も私のわがままを説明しました。回数... -

あしたのために1
文楽舎の前身は、埼玉県の地方都市に作った小さな進学塾です。振り返ってみると、1987年のスタート当初から、現在の文楽舎の姿をにおわせる気配はうっすらとありました。受験指導はしていても、それとは別に、帰国子女に日本語の学習サポートをしたり、不...
12