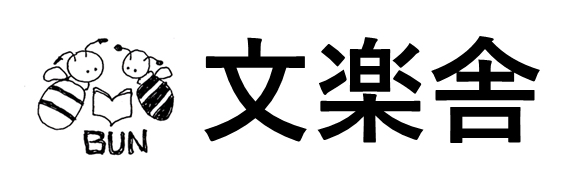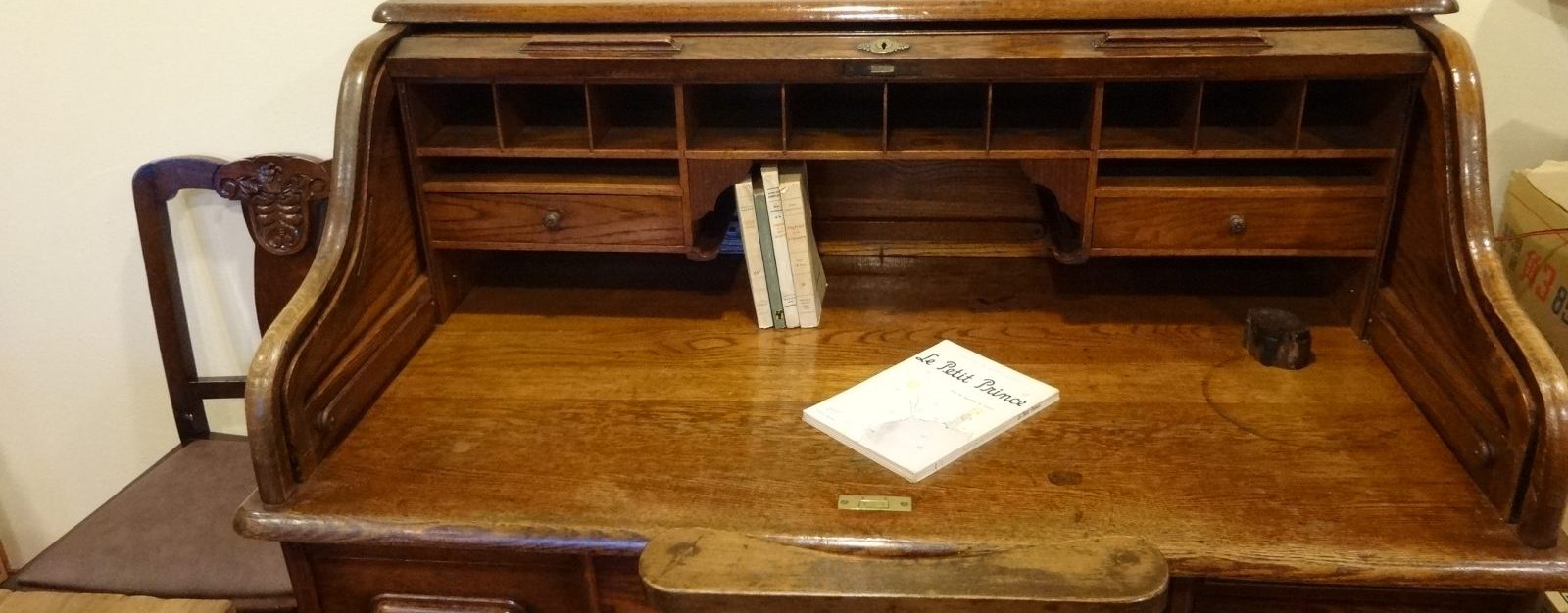(1)子ども、青年の居場所づくり事業


■子どもの居場所「みちくさ」
家庭や学校、また塾や習い事等、様々なコミュニティに自分の居場所を見つけられず、疎外感を感じて一人ぼっちになっている子どもたちが、羽をのばし、心を開放するために集う空間を提供しています。宿題をしたり、おやつを食べたりという日々の生活を大切にしながら、季節のイベントやパーティといった行事などを行なっています。子どものやりたいができる場所を、子どもたちと一緒に作ります。
■青年の心のくつろぎスペース「よりば」
高校生以上の青年たちが、自己有用感を確認しあい、具体的に社会と接点を持つことで得られる自己の存在意義を、形にするお手伝いをします。何かしなければならないことを与えられる場所ではなく、共に語り合い、悩みを共有し、食事を作ったり、ゲームをしたりする中で、具体的な社会活動につながるヒントを発見し、未来の自分自身の有り様を模索する場所です。おとなのやりたいが実現できるアイデアを目指しています。
(2)子ども、青年及びその保護者へのアウトリーチ事業


■困りごとを抱え悩んでいる子どもや青年、またその保護者の方々に対する相談、支援、訪問などをしています。40年以上にわたって子どもたちと関わり、様々な姿を見てきた経験からできるアドバイスや、目の前の困りごとへの対応をしますが、解決を急ぐのではなく、まずは傷を癒やすことから始めます。その後、一緒に悩み、一緒に考え、もし必要がある場合は、行政や専門機関、学校や諸団体との連携もします。
■地域に住んでいる海外にルーツを持つ子どもたちの日本語や学習支援の他、学校と家庭間の連絡事項を伝達しなおしたり(プリント類の翻訳や説明し直し等)、保護者の代わりに学校での面談をしたりといった、学校との連携、学校生活の支援をしています。
(3)子ども、青年の生活支援、学習支援事業


■「まなび」事業
障がい、経済困窮、不登校等により学習につながりにくい子どもの「学び」の支援をしています。望むような学習環境にない子どもたちに、学校授業の補習や塾の受験指導とは異なった一人ひとりに合わせた学習フォローを行なっています。また、個々に進路相談や受験対策もしています。
■「ばんさん」事業
活動日には毎日提供しているおやつ(軽食=ミニチャーハンやそうめん、おにぎりなど)と、毎週金曜日には、「金のばんさん」を提供し、お腹いっぱい食べています。食のアレルギーに対する対応や宗教的配慮を行ないつつも、好き嫌いがあるのも、食べる食べないも自由です。食事を通して、貧困への支援だけでなく、孤食や固食、戸食や小食への対応をしています。
■「ゆうゆう」事業
経済的に厳しい状況下にあるご家庭や、保護者の金銭的価値観の相違から、子どもたちの生活に必要な物が与えられない場合、その支援を行ないます。学校で使用する教材、生活上で必要な物品の他、米や食材の配給をしています。自立過程にあって経済的に厳しい状況にある青年の援助も行ないます。
(4)子ども、青年の社会参画支援及び人づくりを通じた社会活性化に関する事業


■「金の学び(金曜日の学び=テストに出ない大切な学び)」
平和や人権、貧困や気候変動などといった、なかなか正解の出ないテーマについて、年齢枠にとらわれず、みんなで一緒に話し合ったり、ゲームや教材を通して考えたりする時間を持っています。
■体験学習プログラム「おさんぽ」
各界のスペシャリストの方々を訪問したり、資料館、特別企画展などへ出かけたりしながら、多様性を理解し、共生を学びます。出会う人や文化、考え方や価値観など、「みんなちがって、みんないい(金子みすゞ)」を合言葉に、いろいろな社会があることを知り、様々な人々とつながることで、自分が生きていく未来の世界を確かなものとしていきます。
■絵本をアジアに贈ろう「ブックパス」
全国から献本いただいた絵本を海外(フィリピン)に贈る活動を、子どもたちと一緒に行ないます。また、アジアの子どもたち(タイ、カンボジア、バングラデシュ)に、自分たちでできる支援活動を考え、それらを通して子どもや青年たち自身が、社会や世界とのつながりを実感していくプロジェクトです。
(5)関連団体及び関連機関との連携、協働事業


■他のNPO法人や諸団体と協働し、様々な事業を行ないます。
子どもたち、青年たちの支援に関わっている人たちや団体は、どれだけ前向きに取り組んだとしても、自分たち一人だけ、団体一つだけでは支えきれない現状があります。そこでそれぞれの団体が、自分たちの得意分野を活かしつつ、団体間の隙間に子どもや青年がこぼれ落ちることがないよう、緊密な連携を取り合っています。
現在は、多様な学び方を考える団体様や海外ルーツの人々を支援している団体様、ヤングケアラーを支えている団体様などと、助け合っています。









メディア掲載
・季刊「教師の友」誌2016年10-12月号(日本キリスト教団出版局)に活動が紹介される。
・「こころの友」誌2021年2月号(日本キリスト教団出版局)に活動が紹介される。
・季刊「教師の友」誌2021年4月から2024年3月まで、活動の様子が3年間にわたり連載される。
・「ハピネスなかの」2023年冬号(社会福祉法人中野区社会福祉協議会)に、活動の表彰と代表理事のシンポジウムの様子が紹介される。
・月刊「信徒の友」誌2025年1月号に活動が紹介される。